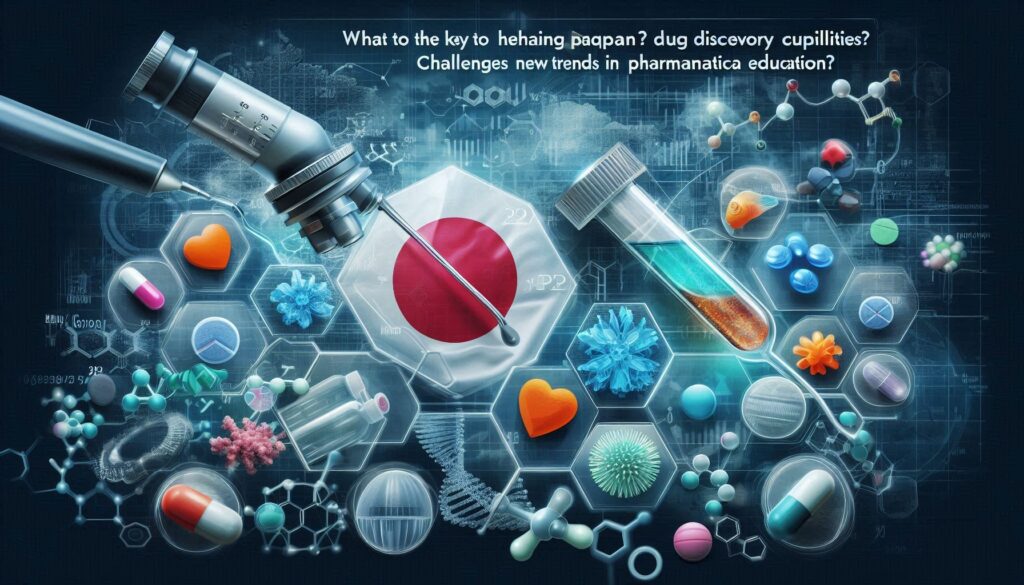1.はじめに:日本の創薬力とは
日本の医療研究において「創薬力」とは、新しい医薬品を発見し、開発し、社会に届けるための総合的な能力を指します。近年、この創薬力の国際競争力が低下しているとの指摘があります。新薬開発には多大なコストと長い時間がかかり、グローバル競争はますます激しさを増しています。
日本でも優れた基礎研究は多いものの、実際に患者さんのもとへ届くまでには「ドラッグラグ」と呼ばれる承認の遅れや、高度な技術を扱える人材の不足など、さまざまな課題が山積しています。今回は2025年時点の現状を見据えながら、これからの薬学教育と創薬研究力強化のポイントを解説します。
2.日本の創薬力が低下している背景
まず挙げられるのが、グローバル市場における日本発医薬品のシェアの減少です。特にバイオ医薬品の分野での後れが指摘されており、高度な分子技術や製造プロセスを活用するための研究基盤が十分に整っていません。これにより海外に先行を許すケースが増えています。
加えて、医薬品価格政策や研究資金の確保も重要な課題です。革新的な医薬品を開発しても、価格の引き下げ圧力が高まり、企業や大学が研究投資をしにくい構造があるといわれています。こうした構造的問題が続くことで、国内での医薬品開発意欲がそがれるという見方も存在します。
さらに、ドラッグラグの問題も残っています。これは海外で承認された医薬品が、日本では承認に時間がかかり、患者さんがすぐに利用できない状況を指します。特に小児用医薬品や希少疾患治療薬など、患者数が少ない領域で深刻です。
3.研究開発環境と人材育成の現状
創薬研究に必要な投資や高度な人材確保が難しい点も、大きな課題の一つです。大学や研究機関が豊富な研究費を得る機会は限られており、基礎研究から応用研究、そして臨床試験までを一貫して支える仕組み(エコシステム)が未成熟といえます。
人材育成の面では、薬学教育が6年制となった後、薬局や病院で活躍する臨床型薬剤師の育成が強化されました。その一方で、基礎研究や新薬開発に特化した人材は、相対的に減少しつつあるとも指摘されています。治験や品質管理に携わる専門家の需要も高まっていますが、十分に応えられていないのが現状です。
こうした背景の中で、岡山大学病院では治験薬剤師を中心に実践的教育を行うほか、大阪大学では「研究型6年制」という形で研究と臨床を融合した教育プログラムを試みるなど、新しい取り組みが芽生えています。広島大学ではGMP教育センターを設立し、国際水準の製造・品質管理を学べる環境を整えています。
4.AIやデジタル技術の活用が切り開く未来
人工知能(AI)やビッグデータなどのデジタル技術は、創薬プロセスを効率化する大きな可能性を秘めています。たとえば、遺伝子情報や大規模な患者データを解析し、新たな創薬ターゲット(薬の作用点)を発見する取り組みは急速に進んでいます。
実際に、AI創薬を導入した研究では、化合物のスクリーニングやリード化合物(有望候補)の最適化期間が短縮し、開発コストを削減した事例もあります。日本国内でも、大手製薬企業と大学の共同研究やスタートアップ企業の活躍が注目されており、将来的な市場拡大が期待されています。
ただし、AIの導入には正確なデータ取得と解析技術が不可欠です。さらに、それを実際の医療現場で活用するためには、医療従事者や研究者がAIの原理や限界を理解し、適切に運用できる体制づくりが必要となります。この点は薬学教育においても見逃せません。
5.実践的な薬学教育が創薬を支える
創薬力を強化するには、大学教育の段階から研究や臨床試験の実際を体験できる環境が欠かせません。たとえば治験では、被験者の選定やデータ管理、国際基準への適合など多岐にわたる知識が求められます。学生時代からそうした場に触れられるプログラムを提供することが重要です。
大阪大学が取り組む研究型6年制プログラムや、岡山大学病院が展開する臨床現場との連携は、学生が学びながら実務を経験できる好例です。こうした試みは、座学だけでは得られない実践的スキルを早い段階で身につけることに直結します。
AIやデジタル技術を活用したカリキュラムも欠かせません。たとえば「AI in Healthcare」や「データサイエンス基礎」といった科目を導入し、シミュレーションラボや演習形式で学ぶ大学も増えています。新しい技術を理解する力が、未来の創薬を支える原動力となるのです。
6.産学官連携とグローバル視点
創薬力を高めるためには、大学(アカデミア)、製薬企業(産業界)、そして行政(政府機関)が密接に連携する「トリプルヘリックス」の考え方が必要です。共同研究や助成金の活用により、新薬の種(シーズ)を効率よく開発し、社会実装を目指す取り組みが各地で進行しています。
広島大学のGMP教育センターでは、国際基準に則った製造管理と品質管理を学べるため、大学と企業の協力体制が充実しています。国際共同治験への参加や外国企業との連携も促進され、これからはグローバルネットワークを活用して新しい治療法や医薬品の開発を進めることが求められます。
研究者や薬学部教員にとっても、グローバル視点は欠かせません。海外の学会や国際共同研究に参加することで、世界最先端の技術や情報に触れる機会が増えます。その経験は学生への教育にも反映され、国内だけでは得られないイノベーションをもたらすでしょう。
7.次世代型薬学教育モデル・コア・カリキュラム
文部科学省が検討中の次期薬学教育モデル・コア・カリキュラムでは、創薬力強化を念頭に置いた内容の拡充が期待されています。たとえば治験や臨床試験の実施意義、臨床開発方法論に関する教育を強化し、新薬開発に直結する人材の育成を目指す構想があるとされています。
この新カリキュラムでは、博士課程プログラムの充実も焦点となります。博士課程では基礎研究から臨床応用までを包括的に学び、AIやデータサイエンスなど最先端の創薬手法を取り入れることを重視します。高度専門職の人材を増やすことで、研究開発の質とスピードを両立させる狙いがあります。
治験や臨床試験に特化した教育プログラムも整備が進んでいます。創薬力構想会議などでも指摘されている通り、国際水準の臨床試験を運用できる人材は非常に限られています。学生時代から倫理的配慮や規制要件、データマネジメントなどを体験する機会を増やすことで、将来的な人材不足を解消する方策となるでしょう。
8.AI・データサイエンスを活用する教育の意義
AI創薬やゲノム創薬といった新しいモダリティ(手法・技術)が注目される中、情報工学やデータ解析技術を組み合わせる教育の重要性が高まっています。ゲノム情報などの大規模データを取り扱うには、統計学やプログラミングの基礎知識が必要です。
名古屋大学の「創薬科学研究科」や京都大学の多分野融合プログラムなど、基礎化学や生物学に加えて工学的アプローチも学べる環境が増えています。さらに第一薬科大学薬学部薬科学科医療データサイエンスコースでは、AI創薬や医療データサイエンスを取り入れたカリキュラムが展開されつつあり、複合的なスキルを学生に提供します。
これらの取り組みが生む最大のメリットは、新薬開発までの時間とコストを削減できる可能性にあるといわれています。高速スクリーニングや構造予測技術は、開発プロセスを効率化し、治療効果の高い医薬品をより早く患者さんに届ける助けとなります。
9.地域医療と創薬を結ぶ視点
日本は高齢化が進行し、地域医療や在宅医療のニーズが高まっています。創薬と聞くと大規模製薬企業の研究開発を想像しがちですが、地域に根ざした医療課題の解決にも新薬の果たす役割は大きいのです。希少疾患や小児医療など、患者数が限られる領域であっても、適切な薬が求められています。
そこで重要になるのが、地域の病院や診療所との連携です。大学の研究だけでなく、地域医療現場での課題や患者さんの声をダイレクトに拾い上げる仕組みが必要です。その情報を新しい薬の開発に生かすことで、社会全体のヘルスケア水準を向上させることができます。
10.創薬人材に求められる基礎と応用
創薬人材を育成する際、特に重要となる科目としては、有機化学や生物科学、薬理学、毒性学などの基礎領域が挙げられます。有機化学では新薬の合成に欠かせない分子レベルの理解を学び、生物科学や薬理学では薬が体内でどう作用するかを知ることができます。
さらに、バイオインフォマティクスやAI活用などの応用科目を学ぶことで、分子設計から臨床試験のプロトコル作成までを俯瞰(ふかん)して考えられるスキルが身につきます。特許や知的財産権についての知識も、研究成果を社会に実装するうえで不可欠です。
多分野を融合するカリキュラムが理想的ですが、それを実現するには時間と労力が必要です。名古屋大学や京都大学のように、他の学部や学科と協力しながらカリキュラムを作る大学が増えているのも、創薬研究を加速させるための一つの流れといえます。
11.今後の政策と教育への期待
日本政府は2025年から2030年にかけて、創薬スタートアップ企業の育成や臨床試験ネットワークの拡大などを含む政策ロードマップを示しています。これには大学の研究力強化や若手研究者の支援も盛り込まれ、イノベーションを生むための土台づくりが進むと期待されます。
薬学教育においては、基礎研究と臨床応用のバランスを取りながら、新しい技術やグローバルな視点を取り入れることが今後の主な方向性となります。世界水準で見ても競争力のある医薬品を生み出すためには、幅広い知識と専門性を持つ人材を育てる必要があります。
これらの施策が実現すれば、日本の創薬力は再び世界に通用するレベルまで高められる可能性があります。多様な人材が国内外で活躍し、新しい医薬品を迅速に患者さんへ届ける未来を築くためには、教育と研究開発の両輪をしっかりと回していくことが不可欠です。
12.まとめと創薬力強化への展望
ここまで見てきたように、日本の創薬力を取り巻く環境は非常に複雑ですが、同時に大きな可能性も秘めています。ドラッグラグ解消やバイオ医薬品の開発促進には、大学や企業、政府が一体となって取り組む必要があります。その基盤として、薬学教育の改革が鍵を握っているのです。
創薬プロセスはターゲットの探索、リード化合物の発見、治験、そして承認までと多段階にわたります。AIやデータサイエンスを活用すれば一部工程を短縮できますが、依然として優れた研究者や専門家の存在が欠かせません。その育成こそが、これからの日本の医療研究を支える大きな柱となるでしょう。
今後は新しいコア・カリキュラムの導入や産学官連携、国際共同研究の拡大により、日本の創薬力がさらに高まることが期待されます。研究成果が実際の臨床現場に届き、人々の健康に貢献できる社会を目指して、一人ひとりが何を学び、どう実践するかが問われる時代に入っています。
免責事項
本記事は、創薬研究や薬学教育に関する一般的な情報を提供するものであり、特定の治療法や研究計画を指示・推奨するものではありません。内容の正確性・最新性を保証できず、医療・研究上の判断は必ず専門家や公的情報源を参照し、自己責任で行ってください。本記事の利用・不利用による損害について当方は責任を負いません。また、記事内容は予告なく変更・削除される場合があります。
本記事は生成AIを活用して作成しています。内容については十分に精査しておりますが、誤りが含まれる可能性があります。お気づきの点がございましたら、コメントにてご指摘いただけますと幸いです。
<a href=”https://amzn.to/3E4KO1O” target=”_blank” rel=”nofollow”> Amazonでこの関連書籍「創薬の課題と未来を考える バイオベンチャーがこれから成長するために必要な8つの話」を見る </a>