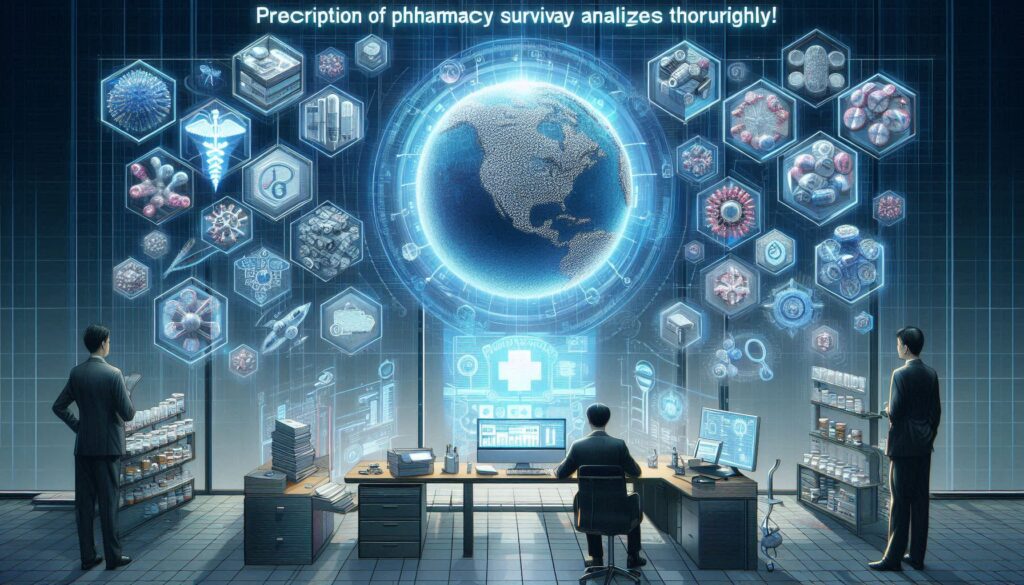1.はじめに:静かに始まった「薬学部の淘汰」、対岸の火事ではありません
医療関係者の皆様、特に大学経営や薬剤師の採用・育成に携わる方々は、最近、薬学部にまつわる厳しいニュースを目にする機会が増えたのではないでしょうか。2024年から2025年にかけて、一部の私立大学で薬学部の「募集停止」や「大幅な定員削減」が相次いで発表され、業界に静かな衝撃が走っています。これは単なる個別の大学の問題ではなく、日本の薬学教育が大きな転換点、いわば「冬の時代」の入り口に立ったことを示す重要なシグナルです。本記事では、この構造変化の深層を読み解き、これからの大学経営、そして医療現場が取るべき戦略について解説していきます。
2.現実を直視する ― 今、薬学部で何が起きているのか?
まずは、この1〜2年で顕在化した衝撃的な事実を正確に把握することから始めましょう。2025年度入試から姫路獨協大学が、続いて2026年度からは医療創生大学が薬学部の新入生募集を停止するという、極めて重い経営判断を下しました。さらに、徳島文理大学(150名→90名)、城西大学(250名→200名)、城西国際大学(110名→60名)など、複数の大学が相次いで入学定員の削減に踏み切っています。これらの動きは、文部科学省が大学の設置認可を厳格化し、定員割れが続く大学に対して厳しい視線を向け始めたことの現れでもあります。もはや、薬学部を設置すれば安泰という「神話」は完全に崩壊しました。この現実は、すべての薬学部と、そこから輩出される薬剤師を受け入れる医療現場にとって、決して他人事ではないのです。
3.なぜ淘汰は始まったのか?深層に横たわる「3つの構造的課題」
このドミノ倒しのような現象は、なぜ今になって始まったのでしょうか。その背景には、長年にわたって蓄積されてきた、避けては通れない3つの構造的な課題が存在します。
【課題1】志願者減と定員充足率の低下が招く「負のスパイラル」 最大の要因は、18歳人口の減少という抗いがたい潮流と、2000年代以降に急増した薬学部の「供給過多」です。限られたパイ(受験生)を多くの大学で奪い合う構図となり、多くの私立大学で定員割れが深刻化しています。定員を充足させるために、入学者の学力基準を下げざるを得ない状況は、教育の質の維持を困難にします。結果として、6年間で卒業できない学生や、国家試験に合格できない学生が増加。これが大学の評判を下げ、さらに志願者が集まらなくなる…という、抜け出すことの困難な「負のスパイラル」に陥ってしまうのです。このスパイラルは、大学経営を根底から揺るがす深刻な問題です。
【課題2】薬剤師国家試験という「質の最終防衛ライン」 薬剤師になるための最終関門である国家試験は、近年、全体の合格率が7割を下回る年が続くなど、決して容易な試験ではありません。特に、新卒学生の合格率には大学間で大きな差が生まれており、合格率が低い大学は受験生から敬遠される傾向が強まっています。国家試験は、いわば薬学教育の質を担保する「最終防衛ライン」です。しかし、その手前の大学教育の段階で学力や学習意欲にばらつきが大きくなっている現状が、この低い合格率に反映されていると言えるでしょう。大学側には、入学から卒業、そして国家試験合格まで、学生を確実に引き上げる教育体制の再構築が厳しく問われています。
【課題3】「薬剤師は余る」は本当か?需給バランスの変化とミスマッチ 「近い将来、薬剤師は供給過剰になる」という需給見通しが、厚生労働省の検討会などで議論されています。この見通しが、薬学部への進学をためらわせる一因になっていることは否めません。しかし、この問題をより深く見ると、単純な「過剰」ではなく、深刻な「ミスマッチ」が起きていることが分かります。つまり、都市部では充足していても地方では不足していたり、調剤業務中心の薬剤師は充足していても、在宅医療やがん、緩和ケアといった高度な専門性を持つ病院薬剤師はむしろ不足していたりするのです。国が推進する「かかりつけ薬剤師」や「地域連携薬局」の役割を担える、質の高い薬剤師へのニーズは、今後ますます高まります。問題は、今の大学教育が、その新しいニーズに応えられる人材を十分に育成できているか、という点にあるのです。
4.未来を拓く薬学部経営とは?コンサルタントが提言する「3つの生存戦略」
この厳しい時代を乗り越え、社会から真に必要とされる薬学部であり続けるためには、従来の経営モデルからの大胆な転換が不可欠です。ここでは、私たちが提案する3つの生存戦略をご紹介します。
【戦略1】「量の経営」から「質の経営」へ ― 勇気ある定員適正化 まず取り組むべきは、自学の教育力に見合った規模まで定員を絞り込む「定員適正化」です。これは単なる縮小ではなく、少数精鋭教育へと舵を切ることで、教育の質を高め、学生一人ひとりへのサポートを手厚くするための戦略的な投資です。定員を絞り込むことで入試の競争率が高まり、質の高い学生を確保しやすくなります。さらに、学内の様々なデータを収集・分析し、教育改善や経営戦略に活かす「教学IR(Institutional Research)」を本格導入し、エビデンスに基づいた教育改革を断行することが重要です。質の高い教育は、国家試験合格率の向上、そして卒業生の社会での活躍につながり、結果として大学のブランド価値を向上させるのです。
【戦略2】”尖った”専門性で差別化を ―「何でも屋」からの脱却 すべての薬学部が同じような教育を提供していては、価格競争や立地競争に巻き込まれるだけです。これからは、自学の強みを最大限に活かした「専門特化」が生き残りの鍵となります。例えば、系列に医学部を持つ大学であれば「がん専門薬剤師」、地域の高齢化が進んでいる大学であれば「在宅医療・老年薬学」、あるいは「AI創薬・データサイエンス」といった先進領域に特化するなど、”尖った”カリキュラムを構築するのです。大学が提供する教育プログラム全体の組み合わせを見直す「カリキュラム・ポートフォリオ改革」を行い、他大学にはない明確な特色を打ち出すことで、「その専門性を学びたい」という意欲の高い学生を全国から惹きつけることが可能になります。
【戦略3】地域医療との「運命共同体」を築く ― エコシステムの構築 大学がキャンパスの中だけで教育を完結させる時代は終わりました。地域の病院や薬局と強固な連携体制を築き、実習、研究、そして就職までを一体的に捉えた「エコシステム」を構築することが求められます。例えば、地域の基幹病院や認定薬局と教育連携協定を結び、教員が臨床現場に出向いたり、現場の薬剤師が大学で教えたりする人事交流を活発化させます。また、地域の医療課題をテーマにした共同研究や、卒業生が地域の医療機関に就職し、リーダーとして活躍する好循環を生み出すのです。大学が地域医療のハブ(拠点)として機能することで、地域にとってなくてはならない存在となり、その価値は揺るぎないものになるでしょう。
5.この変革期に、医療現場と未来の薬剤師がすべきこと
この薬学教育の大転換は、大学だけの問題ではありません。薬剤師を受け入れる医療現場、そしてこれから薬剤師を目指す人々にも、新たな視点と行動が求められます。
【医療機関(病院・薬局)の皆様へ】 新卒薬剤師の採用基準を、今一度見直す時期に来ています。これからは、単に出身大学の偏差値だけでなく、「その大学がどのような教育理念を持ち、どんな専門性を持つ人材を育成しているのか」を深く見極める必要があります。有望な大学とは積極的に連携し、実習生の受け入れや共同での人材育成プログラムに関わることで、自院の未来を担う優秀な人材を早期に確保・育成することにつながります。大学の淘汰は、採用市場における薬剤師の質の「二極化」を加速させる可能性があることを、ぜひ念頭に置いていただきたいと思います。
【薬剤師を目指す学生・受験生の皆様へ】 これからの大学選びは、これまで以上に慎重さが求められます。国家試験の合格率や卒業率といった基本的なデータはもちろんのこと、「その大学でしか学べない専門性は何か」「実務実習の連携先は充実しているか」「卒業生はどのような分野で活躍しているか」といった、教育の「質」に関する情報を多角的に収集しましょう。6年間の学びは、あなたの薬剤師としてのキャリアの土台を築く、非常に重要な期間です。目先の偏差値や知名度だけでなく、自分が将来どのような薬剤師になりたいのかを真剣に考え、そのビジョンを実現できる大学を選ぶという視点が、あなたの未来を大きく左右します。
6.まとめ:淘汰の時代は、未来の医療を創造するチャンスである
薬学部の募集停止や定員削減のニュースは、一見すると暗い話題に思えるかもしれません。しかし、これは日本の薬学教育が、過去の「量の拡大」路線を反省し、これからの社会が本当に求める「質の高い薬剤師」を育成するための、健全な変革の始まりと捉えるべきです。この淘汰の時代を乗り越え、明確なビジョンと戦略を持って改革を断行した大学だけが、未来の医療を担う人材育成の拠点として輝き続けるでしょう。そして、そうした大学から巣立つ質の高い薬剤師こそが、地域医療を支え、国民の健康に貢献していくのです。大学、医療機関、そして未来の薬剤師たちが、この歴史的な転換点を好機と捉え、共に新しい薬学教育の姿を創造していくことを、専門家として心から期待しています。
免責事項
本記事は、公開情報に基づき、情報提供を目的として作成されたものです。内容の正確性や完全性を保証するものではありません。記事に含まれる意見や将来の予測に関する記述は、あくまで執筆者個人の見解です。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害や不利益についても、当方は一切の責任を負いません。最終的な意思決定は、ご自身の判断と責任において慎重に行ってください。
本記事は生成AIを活用して作成しています。内容については十分に精査しておりますが、誤りが含まれる可能性があります。お気づきの点がございましたら、コメントにてご指摘いただけますと幸いです。
Amazonでこの関連書籍「これが私の薬剤師ライフ 6年制卒50人がキャリアを語る」を見る