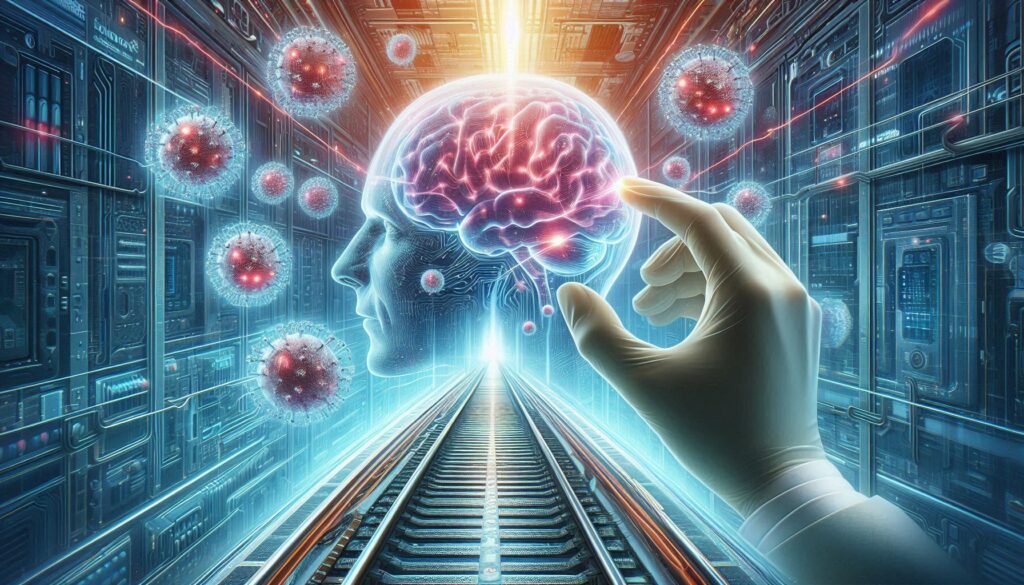1.はじめに
1994年「国際アルツハイマー病協会」(ADI)は、世界保健機関(WHO)と共同で毎年9月21日を「世界アルツハイマーデー」と制定し、この日を中心に認知症の啓発を実施しています。また、わが国でも2024年1月に施行された「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」において、国民の間に広く認知症についての関心と理解を深めるために、毎年9月21日を「認知症の日」、9月を「認知症月間」と定めています。さて、「アルツハイマー病は、もう治らない病気ではないかもしれない」――。近年、原因物質に直接作用する新薬の登場で、私たちはそんな希望を手にし始めました。しかし、治療の最前線では、まだ大きな壁が立ちはだかっています。それは、「薬が脳の中に届きにくい」という問題です。どんなに優れた薬も、目的地である脳に届かなければ意味がありません。今回は、この難攻不落の壁を突破するために世界中の研究者が挑んでいる、驚くべき最新技術について、専門家が分かりやすく解説します。
2.なぜ薬は脳に入れない?鉄壁のバリア「血脳関門」の秘密
私たちの脳は、体の中で最も重要な器官です。そのため、血液中の有害物質やウイルスなどが簡単に入り込まないよう、非常に強力なバリア機能を持っています。これが「血脳関門(けつのうかんもん)、BBB」です。脳の血管にある特殊な構造で、まるで厳重な警備システムが敷かれた「検問所」のように、脳に必要な栄養素(ブドウ糖やアミノ酸など)だけを選んで通し、不要なものや危険なものはシャットアウトしています。
この血脳関門の警備は非常に優秀で、アルツハイマー病の新薬である「抗体医薬」のような、サイズが大きな分子も「部外者」と見なして通してくれません。実際に、点滴で投与された薬のうち、脳内に到達できるのは、全体のわずか0.1%以下とも言われています。この問題を解決しない限り、薬の効果を最大限に引き出すことはできません。そこで科学者たちは、この鉄壁の関門を突破するための、様々な画期的な作戦を開発しているのです。
3.作戦その1:「正規の通行手形」で関門をスマートに通過する!
血脳関門は鉄壁ですが、脳に必要な栄養素を通すための「正規の入口」は存在します。その一つが、血液中から鉄分を取り込むための「トランスフェリン受容体(TfR)」という”ドア”です。このドアは、トランスフェリンという鉄を運ぶタンパク質が持つ「通行手形」を見せると開きます。そこで研究者たちは、アルツハイマー病の薬に、この通行手形をくっつけることを思いつきました。
この「偽造通行手形」を持った薬は、検問所の警備員であるトランスフェリン受容体を上手に利用して、堂々と脳の中へと入っていくことができます。ある研究では、この技術によって薬の脳への移行率が、なんと55倍にも向上したと報告されています。さらに、副作用を減らしながら脳内での薬の分布を改善する改良技術(ATV技術)も開発されており、実用化に最も近いアプローチの一つとして大きな期待が寄せられています。
4.作戦その2:「音の力」で一時的に門をこじ開ける!
「通行手形がダメなら、一時的に門をこじ開ければいいじゃないか」という、非常に大胆な発想もあります。それが「集束超音波(しゅうそくちょうおんぱ)」という技術です。これは、ヘルメットのような装置から、ごく微細な泡(マイクロバブル)を血流に乗せて脳に送り込み、そこに体外から超音波を当てるというものです。超音波でマイクロバブルが振動すると、その力で血脳関門にごくわずかな隙間が一時的に生まれ、その瞬間に薬が脳内へと流れ込みます。
まるでSF映画のような話ですが、臨床試験では素晴らしい結果が出ています。2024年に権威ある医学誌に発表された研究では、集束超音波を使った脳の領域では、使わなかった領域に比べて薬の量が5~8倍に増加。その結果、アルツハイマー病の原因物質であるアミロイドβが、半年間で平均32%も減少したのです。特定の脳領域を狙って薬を届けられる可能性もあり、画期的な治療法として注目されています。
5.作戦その3:「鼻から脳へ」の秘密の近道を使う!
血脳関門という正面ゲートがダメなら、”裏口”を探す研究も進んでいます。その最も有力なルートが「鼻」です。実は、鼻の奥にある嗅神経(においを感じる神経)は、脳と直接つながっています。そのため、薬を点鼻薬のように鼻から投与することで、血脳関門をバイパスして直接脳に送り届ける「経鼻投与(けいびとうよ)」というルートが研究されています。
この方法は、注射も必要なく、患者さんが自宅で手軽に治療できる可能性があるため、非常に魅力的です。ただ、そのままでは脳に届く量が少ないため、薬が細胞の中に入り込みやすくする特殊なペプチド(アミノ酸の短い鎖)と一緒に投与することで、脳への移行率を大幅に高める工夫がなされています。マウスの実験では、脳内の炎症を抑える効果も確認されており、体に優しい非侵襲的な治療法としての未来が期待されています。
6.作戦その4:「超小型カプセル」に薬を隠して運び込む!
薬をそのまま運ぶのではなく、特別な「ナノ粒子」という超小型のカプセルに入れて脳に送り込む、”運び屋”を利用する作戦も有望です。ナノとは10億分の1メートルという非常に小さな単位で、このサイズの粒子は体内で特殊な振る舞いをします。研究者たちは、薬をこのナノ粒子に搭載し、さらにその表面に、先ほど登場した「トランスフェリン受容体」に認識される”通行手形”を貼り付けました。
この運び屋は、血脳関門を効率的に通過できるだけでなく、脳の中で狙った場所に薬を放出するように設計することも可能です。ある研究では、粒子の形を球状ではなく棒状にすることで、脳への集積率が約7倍も向上したと報告されています。薬を守りながら確実に目的地まで届ける、まるでミサイルのような精密な薬剤運搬(ドラッグデリバリー)技術として、開発競争が繰り広げられています。
7.作戦その5:「二つの武器を持つ抗体」で効率アップ!
従来の抗体医薬は、病気の原因(アミロイドβ)を攻撃する「武器」の機能しか持っていませんでした。そこで、「血脳関門を通過する能力」と「病気の原因を攻撃する能力」の二つを、一つの分子に持たせたスーパー抗体が開発されています。これが「バイスペシフィック抗体(二重特異性抗体)」です。
この抗体は、片方の腕で血脳関門の”ドア”を掴んで中に入り、もう片方の腕で脳内のアミロイドβを攻撃するという、一人二役をこなすスゴ腕の兵士です。これにより、脳への移行効率と治療効果の両方を同時に高めることができます。実際に、あるバイスペシフィック抗体は、従来の抗体に比べて4~5倍も効率よく脳に移行することが示されており、次世代の抗体医薬の主流になる可能性を秘めています。
8.希望の未来へ:アルツハイマー病治療は新たな時代へ
今回ご紹介した技術は、まだ研究開発段階のものも多く、すぐに誰もが受けられる治療法になるわけではありません。しかし、これらの革新的なアプローチは、アルツハイマー病治療が直面していた大きな壁を打ち破るための、確かな光です。将来的には、これらの技術を複数組み合わせる「ハイブリッド治療」も考えられています。
より少ない薬の量で、より高い効果を得ることができれば、現在課題となっている副作用(ARIA)のリスクを大幅に減らせるかもしれません。そして、患者さんの身体的な負担や高額な医療費といった問題も、大きく改善される可能性があります。
世界中の研究者たちのたゆまぬ努力によって、アルツハイマー病の原因に立ち向かい、その進行を止め、さらには予防することも夢ではない時代が、すぐそこまで来ています。この記事が、皆さまにとって未来への希望を感じる一助となれば幸いです。
免責事項
本記事は、アルツハイマー病治療に関する科学的研究の動向について、一般の方向けに情報を提供することを目的としています。医学的な助言、診断、または治療に代わるものではありません。記事の内容については、執筆時点での情報に基づき正確性を期しておりますが、その完全性や最新性を保証するものではありません。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる結果についても、一切の責任を負いませんのでご了承ください。ご自身の健康状態や治療に関する判断は、必ず医師や専門の医療機関にご相談ください。
本記事は生成AIを活用して作成しています。内容については十分に精査しておりますが、誤りが含まれる可能性があります。お気づきの点がございましたら、コメントにてご指摘いただけますと幸いです。
Amazonでこの関連書籍「抗アミロイドβ抗体薬治療を見据えたアルツハイマー病診療: 実臨床からみたレカネマブ・ドナネマブ治療の実際」を見る